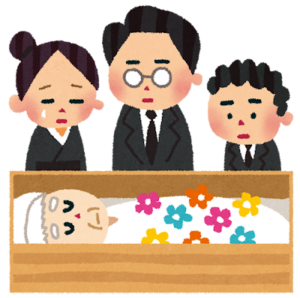「法名って何?浄土真宗の意味と生前に授かる方法を徹底解説」― 仏弟子として生きる安心を得るために ―

法名を知らずに仏事を進めていませんか?
「法名ってよく聞くけど、正直よくわからない…」「戒名と何が違うの?」「生きているうちに授かる意味ってあるの?」
そう感じている方は少なくありません。特に浄土真宗においては「戒名」と「法名」は根本的に意味が異なり、理解しておくことで仏事や人生の終い方に安心が持てるようになります。
この記事では、浄土真宗の法名について、意味・構成・受け方・費用・生前授与の流れまでを網羅的にわかりやすく解説します。読み終えたとき、あなたはきっと「仏弟子として生きる自信」を持てるはずです。
浄土真宗の「法名」とは?
法名は仏弟子の名前
浄土真宗における「法名(ほうみょう)」とは、阿弥陀如来の救いに帰依した人に与えられる仏弟子としての名前です。
他宗派の「戒名」が出家修行者の誓いに基づくのに対し、浄土真宗では「信仰による救い=他力本願」を前提とし、法名は信仰の証とされます。
なぜ「釋(しゃく)」が付くのか?
法名の冒頭には「釋(しゃく)」という字が付けられます。これは「釈迦(しゃか)族の弟子」であることを示しており、仏弟子としての自覚を表す記号です。
たとえば、「釋○○」という法名は、仏門に入ったことを意味します。
戒名との違いは?混同しがちなポイントを整理
多くの人が「戒名=法名」と思いがちですが、浄土真宗では「戒律」という概念がないため戒名は使用せず、法名のみを用います。
| 比較項目 | 法名(浄土真宗) | 戒名(他宗派) |
|---|---|---|
| 意味 | 仏弟子の証 | 戒律を守る誓い |
| 主体 | 他力本願 | 自力修行 |
| 生前授与 | 可(推奨) | 一部可 |
法名の構成と読み方を知ろう
一般的な法名の形式
浄土真宗の法名は以下のように構成されます:
- 釋(しゃく)+2文字の名前 → 通常形式(例:釋 慶順)
- 院号+釋+名前 → 特別形式(例:信光院釋 慶順)
※ 院号は特別な貢献者などに贈られる尊称で、全員に付くわけではありません。
名前の付け方と由来
名前には、本人の生前の性格・生き方・俗名の一部などが反映されることが多いです。たとえば「誠実な人」であれば「誠」など、意味ある漢字が使われます。
法名は生前にもらえる?帰敬式とは
生前授与のメリット
「法名は死んだ後にもらうもの」と思っていませんか?
実は浄土真宗では生前に受ける「帰敬式(ききょうしき)」で授与することが本来の姿です。
生きているうちに仏弟子となることで、人生の指針や安心感が得られるのが最大のメリットです。
帰敬式の流れ
- 菩提寺に相談
- 日程調整と準備
- 寺院で帰敬式を受ける(読経・授与)
- 法名が授かる
費用の相場は?法名にかかるお布施の話
生前に法名を授かるためのお布施は、地域や寺院によって異なりますが、おおよそ以下が目安です。
| 内容 | お布施相場 |
|---|---|
| 生前の帰敬式 | 5,000〜10,000円 |
| 葬儀時の法名授与 | 3万〜10万円程度 |
| 院号付き法名 | 10万〜30万円以上 |
※ 菩提寺と相談し、無理のない範囲で納めることが大切です。
法名を授かった後の準備:法名軸と位牌
法名軸とは?
法名を記した掛け軸のことを「法名軸」と呼びます。仏壇に飾ることで、その人が仏弟子であることを示します。
位牌への記載
浄土真宗では、位牌を使わず過去帳や法名軸を用いることが多いですが、使う場合も釋〇〇の形式で記載されます。
よくある質問Q&A
Q:法名は誰でも受けられる?
→ はい。浄土真宗の信者であればどなたでも帰敬式を受けて法名を授かれます。
Q:家族が法名を受けたい場合は?
→ 一緒に帰敬式を受けることも可能です。事前に寺院に相談しましょう。
Q:すでに故人になった場合は?
→ 死後に法名を授かることも可能ですが、生前授与がより望ましいとされています。
まとめ:法名を知ることで、人生に安心と信仰を
浄土真宗における法名とは、ただの「名前」ではなく、仏弟子としての誓いと安心の象徴です。
生前に授かることで、「南無阿弥陀仏」と唱える意味がより深くなり、自分の死後の不安も薄れていくことでしょう。
次の一歩:菩提寺に相談してみよう
もし「自分も法名をもらいたい」「親にも伝えておきたい」と思ったら、まずはご縁のある菩提寺に連絡をしてみましょう。
帰敬式の日程やお布施、準備するものを丁寧に案内してくれます。
あなたが仏弟子として、これからの人生を安心して歩めるように。