浄土真宗のお葬式ガイド|西本願寺式の流れ・費用・マナーを徹底解説
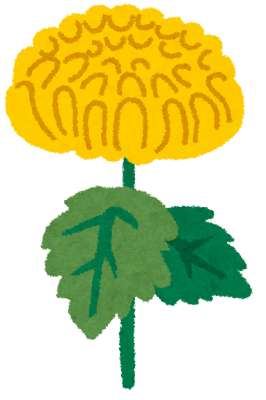
この記事で解決できる3つの問題
浄土真宗(特に西本願寺派)のお葬式を控えている、もしくは参列予定の方は、こんな悩みはありませんか?
- 浄土真宗のお葬式はどんな流れで行われるの?
- 葬儀にかかる費用やお布施の相場が分からず不安…
- 弔いの場での服装やマナーに自信がなく、恥をかきたくない
この記事では、浄土真宗のお葬式が初めての方でも安心して臨めるよう、西本願寺式の特徴から具体的な流れ、費用、マナーまでわかりやすく解説します。この記事を読めば、不安や疑問が解消し、穏やかにお別れの時を迎えられます。
浄土真宗お葬式の基本|西本願寺式とは?
浄土真宗は日本の仏教宗派の中でも最大派閥の一つで、特に「西本願寺(本願寺派)」と「東本願寺(真宗大谷派)」に大きく分かれます。西本願寺は京都に本山があり、全国に多数の檀家がいます。
西本願寺式のお葬式は、阿弥陀仏への帰依を中心とした教義に基づき、極力仏教的な厳格さを保ちつつも「生きとし生けるもの全てへの慈悲」を強調します。特徴としては、
- お経は主に「正信偈(しょうしんげ)」などの念仏中心
- 白木位牌の使用(仮の位牌)
- 戒名(法名)を授けるが、他宗派に比べて「位」より「信心」を重視
などが挙げられます。
浄土真宗お葬式の流れ・タイムライン
浄土真宗のお葬式は、病院や自宅から始まり、枕経、納棺、葬儀当日、法要まで一連の流れがあります。
病院〜搬送〜枕経
亡くなった後、病院から葬儀会場や自宅に遺体が搬送されます。枕経は葬儀前に行う短い読経で、故人の冥福を祈ります。
納棺
専門の納棺師が棺に故人を納めます。白木位牌を棺に置くこともあります。
葬儀当日
僧侶が読経を行い、参列者が焼香をします。西本願寺式では「正信偈」の唱和が中心です。
初七日〜四十九日法要
浄土真宗では、初七日法要は葬儀当日にまとめて行うことが多いです。四十九日法要は家族や親しい人が集まり、忌明けを祝います。
納骨
四十九日や忌明け後に墓地に納骨します。
浄土真宗お葬式の費用とお布施の相場
葬儀費用は地域や規模により異なりますが、浄土真宗のお葬式の費用相場は以下の通りです。
| 項目 | 費用の目安(円) | 説明 |
|---|---|---|
| 葬儀費用 | 50〜150万円 | 会場、祭壇、スタッフ費用 |
| お布施 | 20〜50万円 | 僧侶への謝礼、読経の報酬 |
| お車代 | 1〜3万円 | 僧侶やスタッフの交通費 |
| 精進落とし | 5〜10万円 | 会食費用 |
お布施は特に不透明で心配される方が多いですが、事前に葬儀社や寺院に相場を確認しましょう。
白木位牌とは?意味とマナー
浄土真宗では故人の遺影とは別に、葬儀の間だけ使う「白木位牌(しらきいはい)」を用います。これは仮の位牌で、四十九日までの間、仏壇が用意できない場合に使用されます。
- 白木位牌は紙や白木で作られ、文字は墨で書きます。
- 位牌の表面には故人の戒名や法名、没年月日が記されます。
- 葬儀の後は白木位牌を納骨まで自宅に置き、その後本位牌を用意します。
法要の種類とタイミング
浄土真宗の主な法要は以下の通りです。
- 初七日(しょなのか)
- 四十九日(しじゅうくにち)
- 一周忌(一年目の命日)
- 三回忌(亡くなって3年目)
浄土真宗では特に「初七日」を葬儀当日にまとめて行うのが一般的です。これにより家族の負担が軽減されます。
納骨の方法と時期
納骨は、四十九日や忌明け後に行います。納骨は墓地や納骨堂に故人の骨壺を収めることです。
- 納骨の準備は寺院や斎場と相談しながら進めましょう。
- 西本願寺の檀家であれば、寺院が管理する墓地や納骨堂を利用するケースが多いです。
戒名とは?授かり方と費用
戒名(浄土真宗では「法名」とも言います)は、故人が仏弟子として仏教の教えを受け継いだことを示す名前です。
- 浄土真宗の戒名は「釋(しゃく)」を冠し、性別や信仰の深さによって名称が異なります。
- 授かるには僧侶との話し合いが必要で、お布施とは別に戒名料が発生する場合があります。
浄土真宗お葬式の服装とマナー
服装は喪服(ブラックフォーマル)が基本です。男性は黒いスーツに白ネクタイ、女性は黒いワンピースやスーツに黒いアクセサリーが一般的です。
数珠は浄土真宗独特の「親玉のない丸い玉の数珠」が使われることが多いです。
精進落としのマナー
精進落としは葬儀後の会食で、故人の冥福を祈りつつ参列者の労をねぎらう場です。
- 浄土真宗の精進落としは質素であることが美徳とされます。
- 食事の内容や進行は寺院と相談し、地域の風習に従いましょう。
よくある質問Q&A
Q1. 家族葬でも坊さんは来てもらえる?
A. はい。規模にかかわらず、僧侶による読経は浄土真宗の葬儀の大切な要素です。
Q2. お骨はどのくらい自宅に置いてもいい?
A. 地域や寺院の方針により異なりますが、通常は四十九日までが目安です。
まとめ|安心して浄土真宗お葬式を迎えるために
この記事では、浄土真宗西本願寺式のお葬式に関する基本情報と具体的な流れ、費用、マナーを解説しました。
- 浄土真宗の教えを理解し、葬儀の流れを把握すること
- 費用やお布施の相場を事前に調べて心の準備をすること
- 服装やマナーで恥をかかないようにすること
これらを守ることで、故人に対して敬意を払いながら、家族や参列者が穏やかに見送ることができます。お葬式は悲しみの時ですが、浄土真宗の教えが寄り添い、心の支えになるでしょう。
もしご不明点があれば、葬儀社や寺院に早めに相談して、安心して葬儀を迎えてください。

